福祉・介護の仕事は24時間365日、人の生活を支える大切な職業です。
その一方で、休暇の取り方や夜勤の有無、そして仕事のやりがいや魅力など、働く上で知っておきたい実情があります。
この記事では、最新情報と現場経験者のエピソードを交えながら、福祉・介護職のリアルを解説します。
よくある質問
福祉・介護職は有給休暇を取れますか?
はい。現在は行政の監督も厳しく、有給休暇をしっかり取得できる事業所がほとんどです。ただし、シフト制のため土日祝日が必ず休みとは限りません。
夜勤は必ず経験しなければなりませんか?
職種や事業所によっては夜勤がない場合もありますが、夜勤は利用者の夜間の様子や特有の課題を知る貴重な経験になります。特に若いうちに経験すると対応力が向上します。
福祉・介護職のやりがいは何ですか?
用者の人生の一部に寄り添い、「生」と「死」の両方に向き合える点です。感謝の言葉や笑顔など、お金では得られない感動がやりがいになります。
休暇制度と働き方の実情

近年、行政による労働条件の監督が厳格化されたことで、福祉・介護職でも有給休暇をしっかり取得できる環境が整っています。
ただし、24時間365日ケアが必要な職種のため、土日祝日や年末年始が必ず休みになるわけではありません。
事業所によっては「希望休日制度」を導入しており、平日に休みを取りやすいのが特徴です。
平日の観光地やレジャー施設を満喫できるというメリットもあります。
夜勤の重要性と魅力
夜勤は避けたいと考える人も多いですが、介護現場の夜間は日中では見えない課題や利用者の状態がわかる貴重な時間です。
例えば、認知症の夜間徘徊や昼夜逆転などは夜勤でなければ把握できません。
若いうちに夜勤を経験することで、深い理解と対応力が身につきます。
身体的な負担はあるものの、介護の質を高めるためには大きな意義があります。
福祉・介護職のやりがい
福祉・介護の現場では、「生」と「死」の両方と向き合います。
出産の瞬間に立ち会う助産師が感動を得るように、看取りの場面でも深い感慨が生まれることがあります。
ある職員は、利用者が家族に見守られながら旅立つ姿に、「死を見つめることは生を考えること」と感じたと語っています。
この仕事を続けられる理由
ある職員は、重度の知的障害を持つ利用者との出会いが人生観を変えるきっかけになったと話します。
毎日振り回されるほどの大変さがあっても、帰り際の笑顔と「バイバイ」の一言が、明日も頑張ろうと思わせてくれる──
お金では得られない感動が、この仕事を続ける推進力になります。
まとめ
- 福祉・介護職は休暇制度が整備されており、有給休暇も取得可能
- 夜勤は負担もあるが、利用者理解を深める大切な時間
- 「生」と「死」に向き合うことで得られる深い感動がある
- 人との関わりを通じて、自分の人生観が変わることもある
福祉・介護の仕事は、確かに体力的・精神的に大変な面もありますが、それを超えるやりがいと魅力があります。
人と人が心でつながるこの仕事に、あなたも挑戦してみませんか?
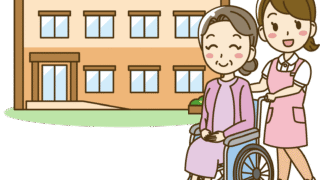
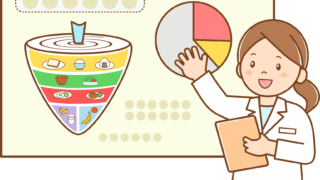

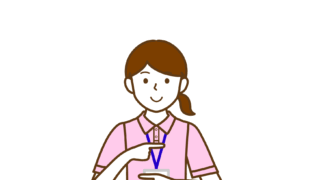
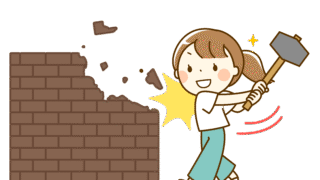


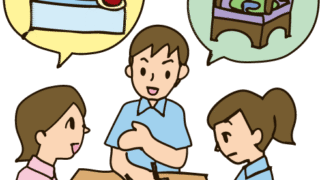
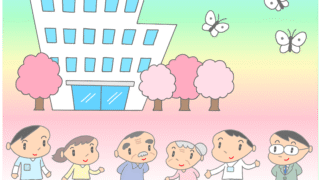

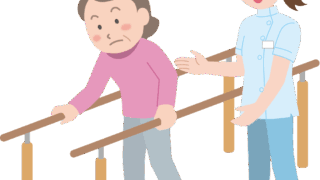
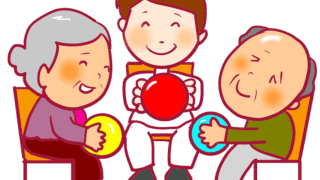



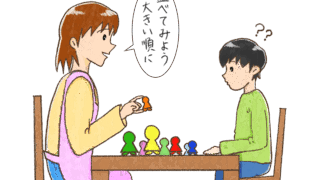





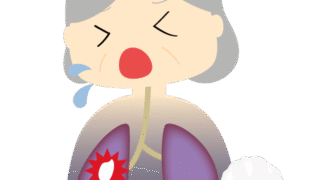

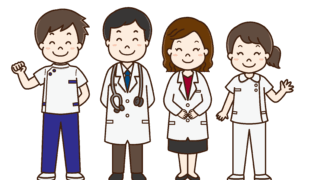

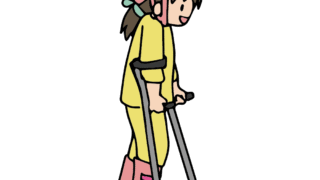

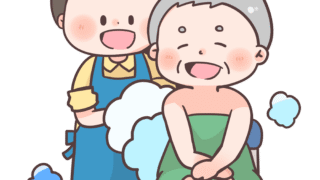
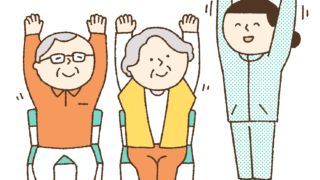
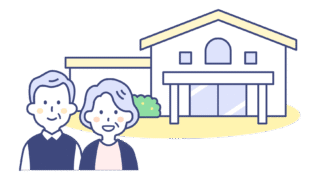

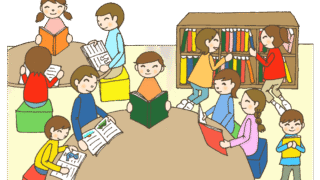
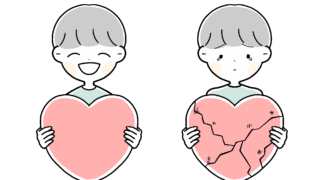
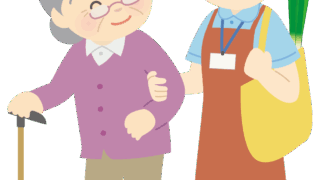


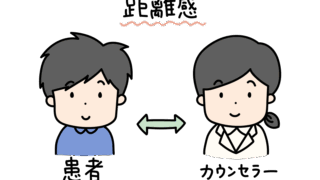
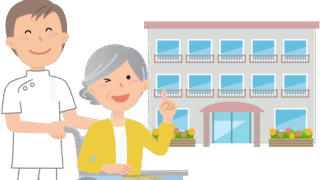
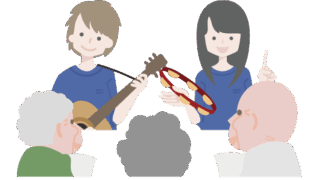

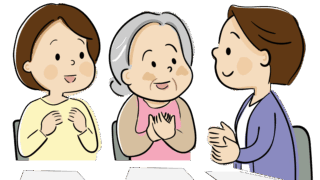
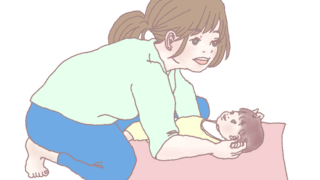
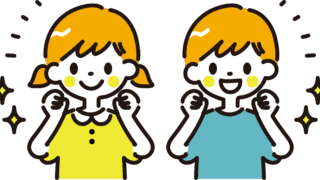

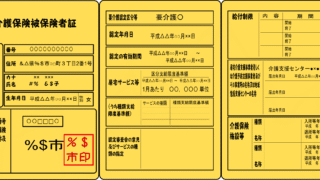
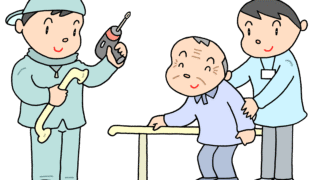
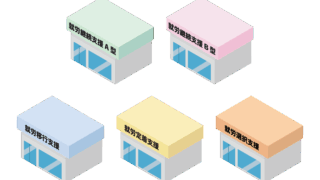
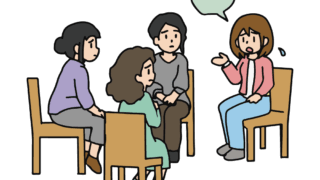


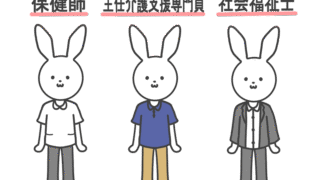
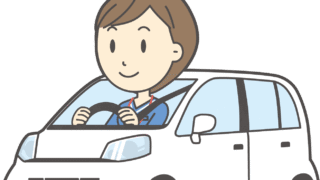

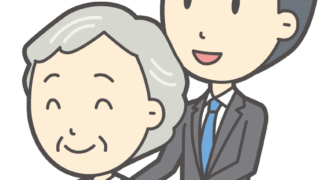

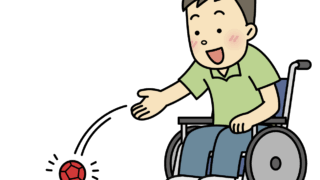


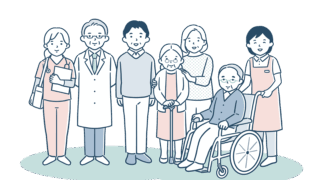


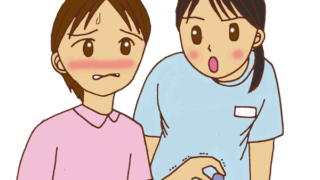
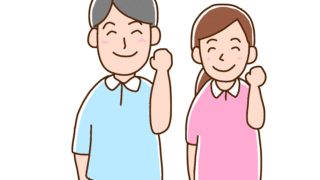


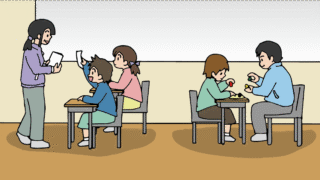
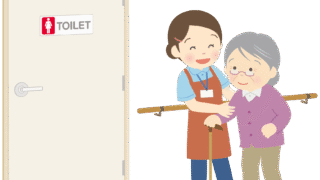

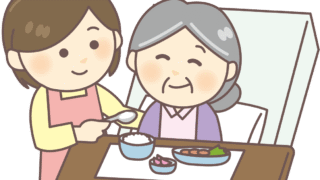
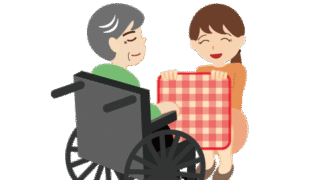
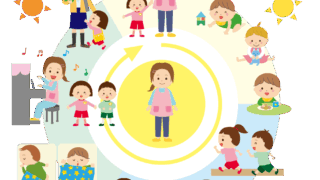

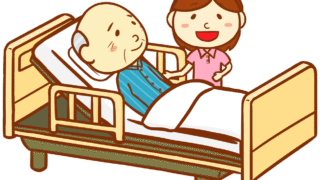



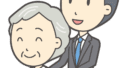
コメント